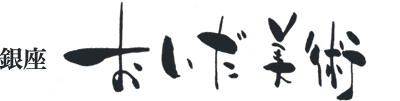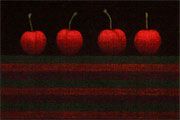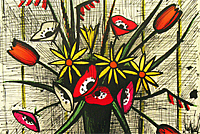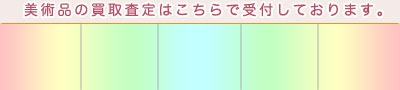窃盗罪について その1
— 2015年9月24日一見無縁そうな美術と法律ですが、知らないとトラブルを招くこともあります。 そんなちょっとした知識を判りやすく説明します。
窃盗罪について その1
絵を所有しているAは、画商のBに頼まれて絵を貸していましたが、Bが倒産しそうだという噂が立ったので、心配になってその絵を返してもらいに行きました。ところがBは不在で、従業員だけしかいませんでした。そこでAは従業員の制止にもかかわらず、その絵を黙って持って帰ってしまいました。ところがこのことで、Aは窃盗の嫌疑で逮捕されてしまったのです。どうして、自分の物を持ち帰っただけなのに、窃盗の嫌疑をかけられたのでしょうか。
そもそも窃盗罪とはどのような犯罪なのでしょうか。
刑法235条は、「他人ノ財物ヲ窃取シタル者ハ窃盗ノ罪ト為シ1年以下ノ懲役ニ処ス」と定めています。事例1の場合、絵の所有者はAですから、所有者が絵を黙って持ち帰ったとしても、「他人ノ財物」ではなく自己の財物であって、窃盗罪に該当しないのではないかが問題となるわけです。
自己の所有物であれば、窃盗罪にはならないのでしょうか。
そうではありません。刑法242条は、「自己ノ財物ト雖モ(いえども)他人ノ占有ニ属シタルトキニハ他人ノ財物ト看做ス(みなす)」と定めています。「占有」とは、物の所持という事実上の状態を意味しています。ですから、事実上、他人が物を所持している状態にあれば、原則として、「他人ノ占有ニ属シタ」状態にあたります。
なぜ、このような法律があるのでしょうか。
窃盗を罰するのは、もともとは所有者を守るためですが、現代社会においては法律関係が複雑化していますので、社会秩序を維持するために、物の所持という事実上の状態それ自体を、保護することとしているのです。ですから、所有者から借り受けた人がいる場合に、所有者が黙って借り受けた人のところから持ち帰るとすれば、やはり窃盗になる可能性があるのです。
それでは、次の場合はどうでしょうか。絵を所有していた画商のCは、Dに絵を売りましたが、値段が高かったので、分割割払いとし、代金を全部払い終わるまで所有権をCに留保することとしました。Cは絵をDに渡したのですが、Dは代金を支払わないままでした。そこでCがDの家へ行ったところ、Dは不在で、奥さんしかいませんでした。Cは奥さんの制止にもかかわらず、その絵を黙って持って帰ってしまいました。
Q:この場合も、Cは窃盗罪になる可能性があるのでしょうか。
A:あります。事例1でご説明したのと同様に、Cから絵を買って引渡しを受けたDは、絵を所持しており、「占有」があります。従って、たとえ絵の所有者であったとしても、CがDのもとから黙って絵を持って帰れば、窃盗罪が成立する可能性があります。事例1も事例2も、同様なのです。
では自分の物でも黙って持ち帰れば、いつでも窃盗罪になってしまうのでしょうか。
ここが微妙なところなのですが、実は、場合によっては、窃盗罪にならないことがあります。形式的には「他人ノ占有ニ属シタ」状態にあったとしても、取り戻す側に権利が存在し、取り戻す際の手段が相当で、権利行使の必要性がある場合には、実質的に違法性がないとして、窃盗罪にならない可能性があるのです。
一般的には、絵の所有者Eが、Fに絵を盗まれた場合に、それをたまたま発見して、窃盗犯人であるFのところから黙って持ち帰った(事例3)としても、Eは窃盗罪にはならないと考えられています。ただ注意しなければならないのは、窃盗犯人Fが絵を第三者であるGに貸したり、売ったりしている場合です。EがGのところから黙って絵を持ち帰った(事例4)とすれば、やはり窃盗が成立する可能性があるのです。
Q:具体的には、どのような場合に窃盗罪にならないのでしょうか。
A:ケースバイケースなのですが、実際に裁判になったケースで、窃盗にならなかった例がありますので、概要をご説明しましょう。
Hが冷房機をIに売りましたが、代金完済まで所有権をHに留保するとの特約がありました。Hは冷房機の引渡を終えたので代金の支払いを求めたところ、Iに弁済の誠意がなかったため、Hは、既に引き渡した冷房機をIのもとから引き上げたのです。
実は、Iは、過去に詐欺で有罪判決を受けたことがあり、今回も当初から代金支払いの能力がない様子でした。Hは取込詐欺の被害にあう可能性があったのです。またIは弁済を一日延ばしにして誠意がなく、他の債権者もIに支払いを求めて集まっていました。そしてHは、Iが弁済すればすぐに元にもどすつもりでした。Iにしてみれば、Hから契約を解除されたとしても抗弁する理由がなく、もしIがその場にいれば、返還を拒否する正当な理由はありませんでした。いわば客観的にはIの承諾が予想された事案だったのです(事例5)。
裁判所は、これらの事情をあげて、Hには、「手段方法において特に不法な点はないし、その行為目的も特に非難の対象となり得るほどのものでもない」、「社会的に相当な行為」として、違法性はなく犯罪は成立しないと判決しました。この場合は、取り戻す際の手段の相当性や、権利行使の必要性が強調されて、窃盗にはならないとされたのです。
Q:窃盗になった例もあるのでしょうか。
A:あります。これも実際に裁判になった例です。
Jは自動車金融業者ですが、車の所有者であるKとの間で、買戻約款付自動車売買契約(Kは自動車を融資金額でJに売り渡して、所有権をJに移転し、返済期限にまでに融資金額に利息を付けた金額をJに支払って買戻権を行使しない限り、Jが自動車を自由に処分できるという契約)を締結しましたが、Kが返済期限に返済しなかったところ、Jが返済期限の翌日、自動車をKに無断で引き上げたのです。Jは高利を得る一方、自動車を転売した方が利益が大きいため、Kの返済が遅れれば直ちに自動車を引き揚げて転売するつもりでした。 しかしKに対してはそのことを秘密にしていました。他方、Kは返済の努力をしていました。ところが、Jは、自動車の点検に必要であるといって預かったキーで密かに合鍵屋に作らせたスペアキーを利用して、Kに断ることなく自動車を引き上げたのです(事例6)。
裁判所は、Jに対し「社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なものというしかない」として、窃盗罪が成立するとしました。この場合、Jは所有者であり権利はあるのですが、手段が相当ではなく、権利行使としてやむを得ず行ったともいえない(必要性がない)として、窃盗にあたるとされたのです。
まとめ:
さて事例1から事例6まで見てきましたが、細かな事実関係次第で、ケースバイケースで窃盗になったりならなかったりすることがお分かりいただけたかと思います。ですから、このような場合には、勝手に一人の考えで行動するより、弁護士に相談されて、そのアドバイスに従って行動されたほうが良いと思います。どうですか、ご参考になりましたか?
美術ヨモヤマ話
 奈良美智の少女を泣かせたのは誰?2024年2月26日
奈良美智の少女を泣かせたのは誰?2024年2月26日 エコール・ド・パリと100年後の今2024年1月31日
エコール・ド・パリと100年後の今2024年1月31日 世界のムナカタってどうやってメイキングされたの?2023年11月27日
世界のムナカタってどうやってメイキングされたの?2023年11月27日 日本とゴッホ2023年11月2日
日本とゴッホ2023年11月2日 マティス展 Henri Matisse:The Path to Color2023年8月7日
マティス展 Henri Matisse:The Path to Color2023年8月7日 越後妻有(えちごつまり)を訪ねて2023年7月19日
越後妻有(えちごつまり)を訪ねて2023年7月19日 マリー・ローランサンとココ・シャネル2023年6月30日
マリー・ローランサンとココ・シャネル2023年6月30日
取扱い作家一覧
画廊紹介

営業時間
月曜日~土曜日(日曜・祝日はお休み)
午前10~午後7時まで
詳しくはこちら
詳しくはこちら
お問合せ
電話番号:03-3562-1740
E-mail:info@oida-art.com
お問合わせフォーム
お問合わせフォーム
LINEでお問合せ
アクセス
画廊店主のひとり言
- 付け馬のついていた画商さん — 2023.12.8
- 一丁あがり、モダンタイムス時代の結婚式 — 2023.8.30
先日、ある地方に住んでいらっしゃるお方(Aさん)より電話がありました。 「B画伯とG画伯の絵を売りたいのですが。」 「保証書と共箱が付いていて、たぶん間違いの...
先日友人の娘さんの結婚式に招待され、参列してきました。 このお二人そもそもはお見合いでお付き合いが始まった話なのですが、お付き合いをするようになりましたら、...
「画廊店主のひとり言」その他のコラムはこちら
作品検索
-
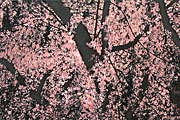
千住博
満開の瀧桜詳細 
斎藤清
春の鎌倉 円覚寺詳細
中島千波
臥龍櫻(2004年)②詳細
熊谷守一
牡丹詳細
岡鹿之助
三色スミレとななかまど詳細
三岸節子
花 ヴェロンにて詳細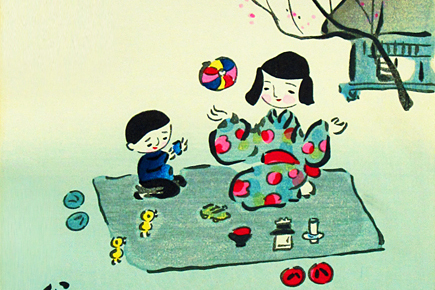
谷内六郎
四季版画より“春”詳細
中島潔
旅立ち詳細
マティス
“ヴェルヴ”より Decor...詳細
デュフィ
熱帯のハーブ(生命の水)詳細
シャガール
デリエール・ル・ミロ...詳細
アイズピリ
花詳細
カトラン
アネモネ2詳細
ジャンセン
仮面と花束詳細
ベルナール・ビュッフェ
アネモネ詳細
ブラジリエ
乗馬詳細
キース・ヘリング
Tree of Life詳細
アンディ・ウォーホル
FLOWERS 2詳細
奈良美智
Miss Spring詳細
村上隆
両手を大きく広げて幸...詳細
ロッカクアヤコ
魔法の手 展覧会ポスター詳細
名和晃平
Untitled(6)(画集「SY...詳細
リャド
バガテルの花詳細
ドラクロワ
恋人達の四季 春詳細
ジェームス・リジィ
TAKE THE A TRAIN TO H...詳細
ヒロヤマガタ
ロコモーティブ詳細
ラッセン
キッシング ドルフィン...詳細
鈴木英人
恋するマイアミ2詳細